※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、広告が含まれる場合があります。
保険料を払いすぎていませんか
「毎月の保険料が家計を圧迫している」「昔入った保険のままで、本当にこれでいいのか不安」「保険の見直しをしたいけれど、何から始めればいいか分からない」――このような悩みを抱えている50代、60代の方は非常に多いです。
実は私も数年前まで、若い頃に勧められるがままに入った保険を、内容もよく分からないまま払い続けていました。月々の保険料は夫婦合わせて4万円近く。年間にすると50万円近くも保険に使っていたのです。しかし、保険を見直したことで、月々2万円以上の節約に成功しました。年間で30万円近くの節約です。
この記事では、シニア世代の皆さんが保険について正しい知識を身につけ、自分に本当に必要な保険を見極められるようになることを目指します。難しい専門用語は使わず、誰にでも分かる言葉で解説していきます。この記事を読めば、無駄な保険料を払わずに済み、安心して老後を迎えることができるようになります。
保険で備えるべきトラブルを理解しましょう
保険に入る前に、まず「保険とは何のために入るものなのか」を理解することが大切です。保険は、めったに起こらないけれど、起こったら大変なことになるトラブルに備えるためのものです。
**保険が必要なのは「低確率・大損失」のトラブルです。**例えば、一家の大黒柱が突然亡くなって収入が途絶える、大きな病気やケガで高額な医療費がかかる、火事で家が全焼する、交通事故で相手に大けがをさせてしまうといった事態です。これらは、起こる可能性は低いものの、いざ起こると何百万円、何千万円という大金が必要になります。普段の貯金では到底まかなえない金額です。
**一方、保険が不要なのは「高確率・小損失」のトラブルです。**例えば、風邪をひいて病院に行く、眼鏡が壊れる、スマートフォンの画面が割れるといった出来事は、よく起こりますが、数千円から数万円程度で解決できます。このようなトラブルには、保険ではなく貯金で対応すれば十分です。保険に入ると、保険会社の運営費や利益が上乗せされるため、結果的に損をすることが多いのです。
**保険の基本は「自分では払えない金額のリスクに備える」ことです。**もし貯金が3000万円あるなら、300万円の医療費は自分で払えるため、医療保険は不要かもしれません。逆に、貯金が50万円しかないなら、500万円の賠償金は払えないため、自動車保険は必須です。自分の貯金額と、起こりうるリスクの金額を比べることが、保険選びの第一歩です。
私が保険を見直したとき、最初にしたのがこの考え方の整理でした。「本当に保険でカバーすべきリスクは何か」を夫婦で話し合い、紙に書き出してみたのです。すると、不要な保険がたくさん見えてきました。
日本の公的保険は思っている以上に充実しています
「保険に入っていないと不安」と感じる方は多いですが、実は日本では誰もが公的保険に加入しており、かなり手厚い保障が受けられます。まずは、この公的保険でどこまでカバーされるのかを知ることが大切です。
**医療費は健康保険で大部分がカバーされます。**病院で診察や治療を受けたとき、私たちが窓口で支払うのは医療費の3割だけです。70歳以上になると2割、75歳以上で一定所得以下の方は1割の負担になります。さらに「高額療養費制度」という仕組みがあり、1か月の医療費が一定額を超えると、超えた分が後から戻ってきます。例えば、年収が約370万円から約770万円の方の場合、どんなに高額な医療費がかかっても、自己負担の上限は月に約9万円です。がんの手術で100万円かかったとしても、実際に払うのは9万円程度で済むのです。
**遺族には遺族年金が支払われます。**一家の大黒柱が亡くなったとき、残された家族は「遺族年金」を受け取ることができます。会社員だった夫が亡くなった場合、妻は月に10万円から15万円程度の遺族年金を受け取れます。子どもがいる場合はさらに増額されます。妻自身のパート収入や貯金と合わせれば、生活を続けることは可能です。もちろん十分とは言えませんが、「収入がゼロになる」わけではないのです。
**介護が必要になったときは介護保険が使えます。**65歳以上で介護が必要になったとき、介護保険を使えばヘルパーさんに来てもらったり、デイサービスに通ったりする費用の9割が公的保険でカバーされます。自己負担は1割だけです。要介護度によって使える金額の上限は決まっていますが、多くの方は公的介護保険の範囲内でサービスを受けられています。
**失業したときは失業保険があります。**会社を辞めたり、リストラにあったりしたときは、一定期間、失業保険(雇用保険)から給付金が受け取れます。これにより、次の仕事を探すまでの間、生活を支えることができます。
このように、日本の公的保険は非常に充実しています。民間の保険に入る前に、まずは公的保険でどこまでカバーされるのかを理解しておくことが重要です。公的保険でカバーできない部分だけを、民間の保険で補えば十分なのです。
本当に必要な保険は3つだけです
公的保険でカバーできない部分を補うために、民間の保険に入ります。しかし、必要な保険は実はそれほど多くありません。ここでは、本当に必要な3つの保険をご紹介します。
**1つ目は掛け捨ての生命保険ですが、これは子育て世帯だけが対象です。**生命保険は、一家の大黒柱が亡くなったときに、残された家族の生活費を保障するものです。しかし、子どもがすでに独立している50代、60代の方には基本的に不要です。夫婦二人の生活なら、遺族年金と妻自身の収入や貯金で十分やっていけるからです。もし子どもがまだ学生で、教育費がかかる場合だけ、子どもが独立するまでの期間限定で加入すれば十分です。
生命保険には「貯蓄型」と「掛け捨て型」がありますが、おすすめは掛け捨て型です。貯蓄型は解約時にお金が戻ってくる代わりに保険料が高く、実は貯金としての効率が非常に悪いのです。同じ金額を保険ではなく銀行に預けた方が、はるかに増えます。掛け捨て型は解約時にお金は戻ってきませんが、その分保険料が安く、必要な保障額を確保できます。
**2つ目は自動車保険で、これは対人・対物無制限のものに入ることが必須です。**車を運転する方は必ず加入しなければなりません。交通事故で相手を死傷させた場合、数千万円から億単位の賠償金を請求されることがあります。これは絶対に自分では払えない金額です。自動車保険には様々なプランがありますが、「対人・対物無制限」を選ぶことが鉄則です。無制限とは、どんなに高額な賠償金でも全額保険でカバーされるという意味です。保険料を節約するために補償額を制限すると、万が一の時に取り返しのつかないことになります。
車両保険(自分の車の修理代を補償する保険)については、車の価値によって判断します。新車や高級車なら入る価値がありますが、10年以上乗っている古い車なら不要です。修理代より車の価値の方が低いため、保険料がもったいないからです。
**3つ目は火災保険で、これは持ち家の方は必須です。**火事で家が全焼したり、地震で倒壊したりしたら、数千万円の損害が出ます。これも自分では到底払えない金額です。火災保険に入っておけば、家の再建費用がカバーされます。賃貸住宅の方も、家財道具を補償する家財保険には入っておくと安心です。
火災保険を選ぶ際のポイントは、補償額を家の再建費用に合わせることです。3000万円の家なら、3000万円の補償が必要です。また、住んでいる地域のリスクに応じて補償内容を選びましょう。水害の多い地域なら水災補償を付け、地震の多い地域なら地震保険も検討します。保険料は会社によって大きく違うため、必ず複数社を比較してください。
この3つ以外の保険は、基本的に不要です。もちろん個人の状況によって必要になることもありますが、多くの方はこの3つで十分なのです。
種類別に保険の必要性を考えてみましょう
様々な保険がありますが、それぞれ本当に必要なのでしょうか。主な保険について、一つずつ考えてみましょう。
医療保険は基本的に不要です。「病気になったら心配だから」と医療保険に入っている方は多いですが、実は公的な健康保険と高額療養費制度で、医療費の大部分はカバーされます。貯金が100万円以上あれば、医療保険なしでも対応できることがほとんどです。月々3000円の医療保険に30年間加入すると、総額で108万円も払うことになります。その保険料を貯金しておいた方が、よほど安心です。ただし、貯金がほとんどない方や、病気で長期入院したときの収入減が心配な方は、最低限の医療保険を検討してもよいでしょう。
**がん保険も基本的に不要です。**理由は医療保険と同じで、高額療養費制度があるため、がん治療にかかる医療費も月に9万円程度で済みます。がんは確かに怖い病気ですが、今は通院で治療できることも多く、必ずしも長期入院が必要とは限りません。貯金があれば、がん保険なしでも対応できます。
**学資保険も効率が悪いためおすすめしません。**子どもの教育費を貯めるための保険ですが、利回りが非常に低く、銀行預金や投資信託で積み立てた方がはるかに効率的です。保険で貯蓄をする時代は終わったと言えます。
**個人年金保険も同様に効率が悪いです。**老後の生活費を確保するための保険ですが、これも利回りが低く、自分で積立投資をした方が有利です。また、途中で解約すると元本割れすることが多く、柔軟性がありません。
**介護保険は公的介護保険があるため基本的に不要です。**前述の通り、65歳以上で介護が必要になったときは、公的介護保険で大部分がカバーされます。ただし、より手厚い介護サービスを受けたい方や、子どもに負担をかけたくない方は検討してもよいでしょう。
**収入保障保険は、子育て世帯には有効です。**これは、一家の大黒柱が亡くなったときに、毎月一定額が遺族に支払われる保険です。生命保険の一種ですが、掛け捨て型で保険料が安く、合理的な設計になっています。ただし、子どもが独立したら不要になります。
このように見ていくと、シニア世代に本当に必要な保険は、自動車保険と火災保険くらいです。医療保険やがん保険、生命保険は、多くの場合不要なのです。
保険を見直す際の5つのステップ
実際に保険を見直すには、どうすればよいのでしょうか。ここでは、具体的な5つのステップをご紹介します。
**ステップ1は、現在加入している保険をすべて書き出すことです。**保険証券を引っ張り出して、加入している保険の名前、保障内容、月々の保険料を一覧にしましょう。生命保険、医療保険、がん保険、自動車保険、火災保険など、すべてリストアップします。夫婦それぞれが加入している保険を合わせると、意外とたくさんあることに驚くはずです。私の場合、合計で8つもの保険に入っていました。
**ステップ2は、それぞれの保険が本当に必要かを判断することです。**前述した「本当に必要な3つの保険」を参考に、各保険の必要性を考えます。「子どもはもう独立しているのに、なぜ生命保険に入っているのか」「医療保険は貯金でカバーできるのではないか」といった視点で見直します。必要性が低い保険には印を付けておきましょう。
**ステップ3は、保険料の総額を計算することです。**月々の保険料を合計し、さらに年間でいくら払っているのかを計算してみてください。おそらく、想像以上の金額になっているはずです。私の場合、年間48万円も払っていることに気づき、衝撃を受けました。この金額を見ると、「本当にこの保険は必要なのか」と真剣に考えるようになります。
**ステップ4は、不要な保険を解約することです。**必要性が低いと判断した保険は、思い切って解約しましょう。「もったいない」「今まで払った保険料が無駄になる」と感じるかもしれませんが、それは間違いです。過去に払った保険料は取り戻せません。大切なのは、これから先、無駄な保険料を払い続けないことです。解約の手続きは、保険会社に電話するか、ホームページから申し込めば簡単にできます。
**ステップ5は、必要な保険の保険料を安くすることです。**自動車保険や火災保険は必要ですが、保険料は会社によって大きく違います。インターネットの保険比較サイトを使えば、簡単に複数社の見積もりが取れます。私の場合、自動車保険を見直しただけで、年間2万円も安くなりました。同じ補償内容でも、会社を変えるだけで保険料が半額になることもあります。
この5つのステップを実践すれば、多くの方は月に1万円から3万円、年間で12万円から36万円の節約ができます。浮いたお金は、旅行や趣味、孫へのプレゼントに使えます。ぜひチャレンジしてみてください。
保険契約で注意すべき3つのポイント
新しく保険に入る際、または既存の保険を見直す際には、次の3つのポイントに注意が必要です。
**1つ目は保障内容をしっかり理解することです。**保険は契約書が分厚く、内容が複雑です。保険の営業担当者は「これは安心ですよ」「みなさん入っていますよ」と言いますが、自分で内容を理解しないまま契約してはいけません。「どんなときに、いくら支払われるのか」「逆に、どんなときは支払われないのか」を必ず確認しましょう。分からないことは、何度でも質問してください。納得できるまで説明してもらうことが大切です。
**2つ目は保険料の負担を長期的に考えることです。**月々3000円の保険料は安く感じますが、30年間払い続けると108万円になります。保険は一度入ると長期間払い続けるものなので、総額でいくらになるのかを計算してみてください。また、年金生活になったときも、その保険料を無理なく払い続けられるかを考えましょう。現役時代は払えても、年金生活では負担に感じることもあります。
**3つ目は更新条件と解約条件を確認することです。**保険の中には、一定期間ごとに更新が必要で、更新のたびに保険料が上がるものがあります。60歳のときは月3000円だったのに、70歳になったら月1万円に跳ね上がるといったケースです。契約前に、更新時の保険料がどう変わるのかを確認しましょう。また、解約時に違約金がかかるのか、途中で解約すると損をするのかも確認が必要です。特に貯蓄型保険は、早期に解約すると払った保険料より戻ってくる金額が少なく、大きく損をすることがあります。
保険の契約は、一度決めると長期間影響が続きます。面倒でも、これらのポイントをしっかり確認してから決めることが、後悔しないための秘訣です。
まとめ 賢い保険選びで老後を豊かにしましょう
保険の見直しは、決して難しいことではありません。正しい知識を持ち、冷静に考えれば、誰でも無駄な保険料を減らすことができます。
まず、保険は「低確率・大損失」のトラブルに備えるものだと理解しましょう。めったに起こらないけれど、起こったら自分では払えないリスクだけを、保険でカバーすれば十分です。
次に、日本の公的保険は非常に充実していることを知りましょう。医療費は高額療養費制度でカバーされ、遺族には遺族年金が支払われます。民間の保険は、公的保険でカバーできない部分だけを補えばよいのです。
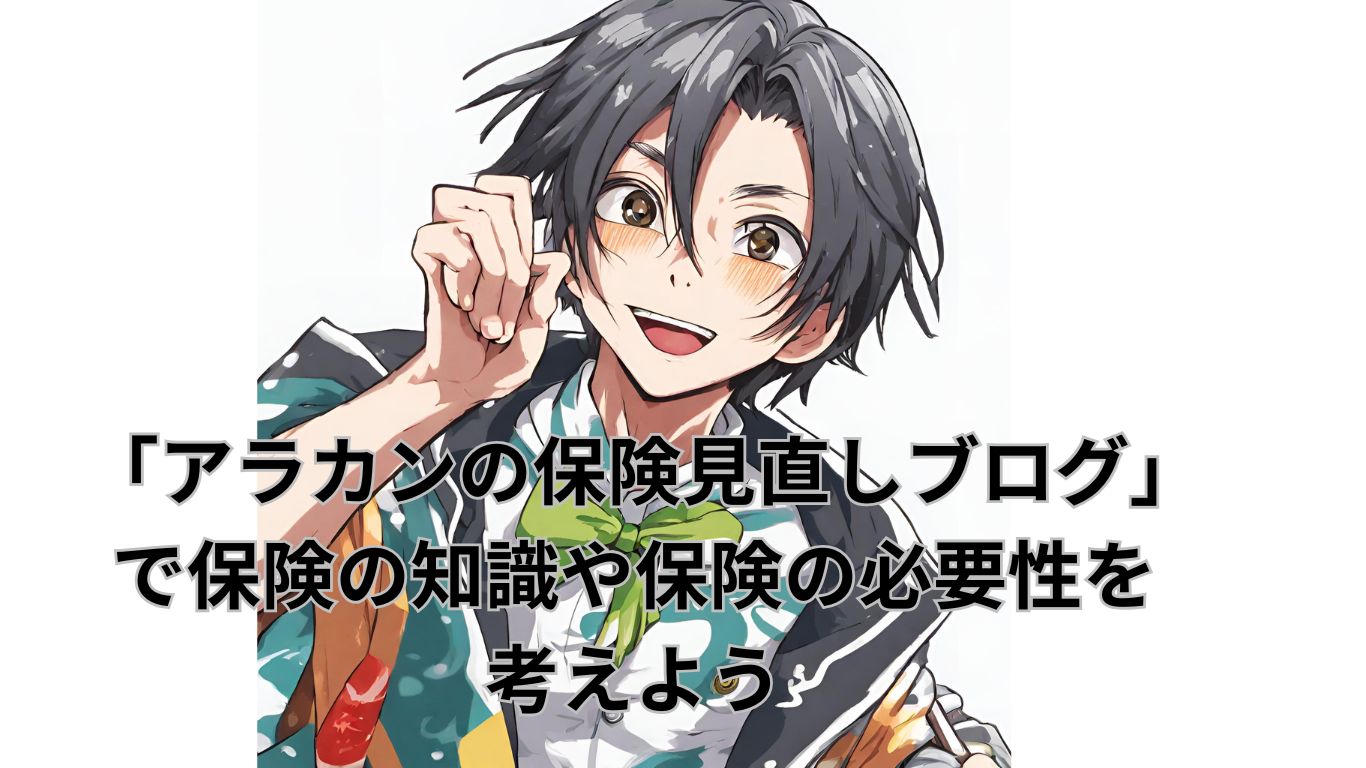


コメント